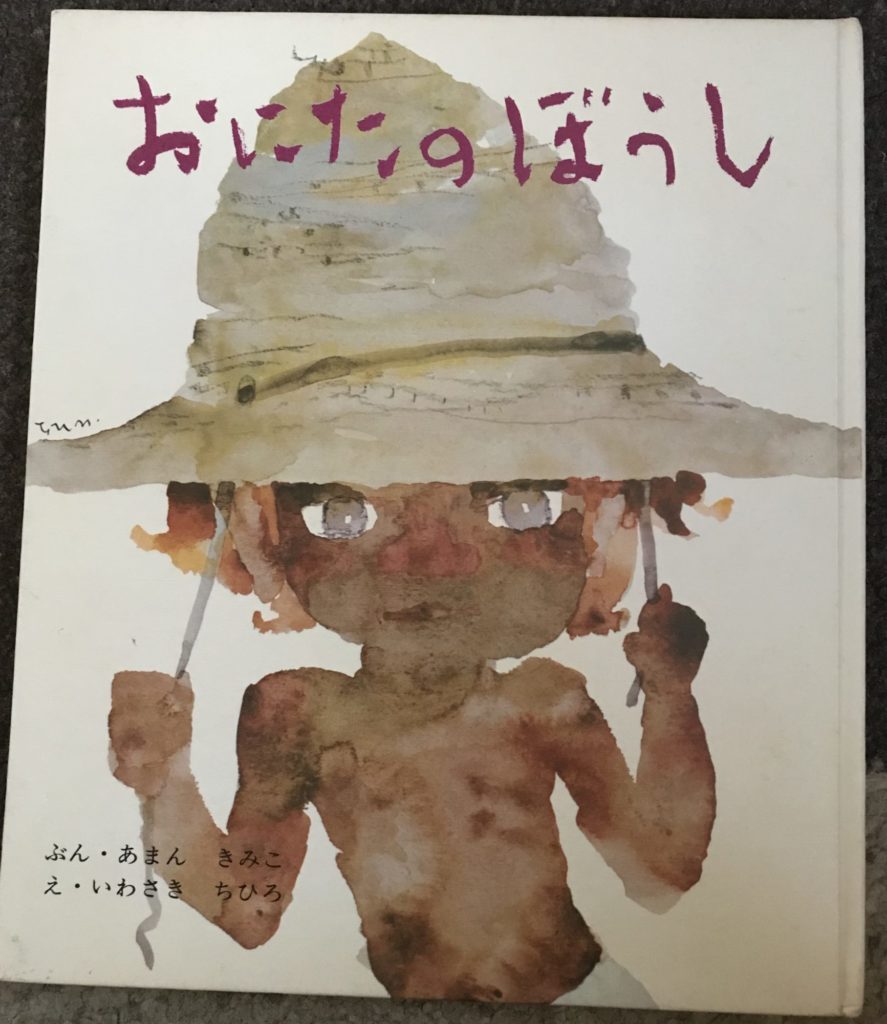インフルエンザ娘が
寝たきりであまりに退屈そうなので、
本を読んであげました。
おにたのぼうし
いわさきちひろさんの絵で有名な作品。
文はあまんきみこさん。
1970年、ポプラ社刊です。
〈あらすじ〉
節分の豆まきの日に、家から追い出された優しい鬼の少年・おにたは、
節分の柊を飾っていない家をみつけ、忍び込みます。
その家には、病気で臥せっているお母さんと
飲まず食わずで看病をしている少女が住んでいて、
おにたは少女のために
節分であまったご馳走だとうそをついて
食べ物を差し入れします。
少女は喜びますが、今日が節分だということに気が付くと
お母さんの病気はきっと鬼の仕業だから、
自分も豆まきをしたいとおにたに打ち明けます。
おにたは、おにだって悪い鬼もいれば良い鬼もいるのに・・・と
悲しくなり、かぶっていた帽子を残して姿を消します。
帽子の中には黒い豆が入っていて、
少女はさっきの子はきっと神様だったんだと思い、
お母さんの病気がよくなりますようにと
願いを込めて、その黒い豆をまきました。
感想
人間は鬼=悪いものというイメージを持っていますが、
鬼の中にも優しい鬼もいれば、恐ろしい鬼もいます。
やさしい鬼は、きっと節分の日には心を痛めているだろう
という空想から、物語は生まれたのではないかと思います。
少女のお母さんを思う優しい気持ちには
ひとつのうそもなく、
「悪い鬼のせいだ」と思いたい気持ちもわかります。
おにたは、人々に嫌悪され排除されて、
自分のことを理解してほしいという
悲痛な思いも持っていますが、
少女の純粋な願いを叶えてあげる方を選びます。
相反する立場に立った時に
人は、相手のことをどこまで
尊重してあげられるのでしょうか?
自己犠牲の精神、というと
それは自己欺瞞なのではないか?
という疑惑がつきまとうのですが、
相手が子供や動物の場合には
美しい、胸の痛みを感じる物語として
成立しうるのだなと思いました。